あなたは勘違いしていませんか?
生前贈与をした時の「生前贈与加算」と「特別受益」は違います。
「生前贈与加算」は、令和5年の税制大綱により3年から7年以内に変更されます。
この事と、「特別受益」の持ち戻しは全くの別物です。
あなたは、ご存知でしたか?
今回は、「生前贈与加算」とは別物の「特別受益」とはどの様なものかをご説明します。

生前贈与があった場合の「特別受益の持ち戻し」とは?
生前贈与があった場合に、遺留分の計算をする際は、生前贈与で先に渡した財産も合わせて計算する必要があります。この取り扱いを「特別受益の持ち戻し」といいます。
民法上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前渡しと考えます。
相続発生前10年以内に行われた生前贈与が、持戻しの対象となります。
これは、「生前贈与加算」と良く勘違いされますが、「生前贈与加算」は相続税法であり、「特別受益」は民法であるため、全くべつのものなのです。
つまり、相続税を計算する時には「生前贈与加算」を持ち戻して計算する必要があり、遺留分を計算する時には「特別受益」を持ち戻して計算する必要があるということです。
特別受益となる生前贈与は、以下のものとされています。
- 『生計の資本となる贈与』
- 『親族間の扶養的金銭援助を超えるもの』
つまり、扶養家族に対して食費や学費、医療費やお小遣いを与えるのは当り前の行為であるため、贈与とは考えないが、その範疇を超えたものは「特別受益」と扱うということです。
「特別受益」に該当するもの
以下のような内容の贈与は「特別受益」に該当します。
「特別受益」に該当しないもの
以下のような内容の贈与は「特別受益」に該当しません。
| 贈与内容 | 説明 |
| 結婚の際の贈与 | 特参金、支度金は、金額が大きければ一般的には、特別受益に当たりますが、 結納金や挙式費用は、特別受益には当たりません。 |
| 貸付金 | 貸付金は贈与ではないため、特別受益には当たりません。 |
| 小遣い・生活費 | 通常は、扶養の範囲内であるた特別受益には当たりません。また、遊興費のための贈与も、特別受益には当たりません。 |
| 新築祝い・入学祝い | 親としての通常の援助の範囲内でなされたお祝いは、特別受益には当たりません。 |
| 学資 (高等教育 (大学等) を受けるための費用) | 被相続人の生前の経済状況や社会的地位を考えると、相続人を大学等へ通わせるのは親としての扶養の範囲内と思われる場合や、共同相続人全員が同程度の教育を受けている場合には、特別受益にあたらないとされることが一般的です。 留学費用も、同様の場合には、特別受益にあたらないとされるのが、一般的です。 |
| 生命保険金 | 原則として、特別受益には当たりません。 ただし例外的に遺産の全体からみて、保険金を受け取る相続人と受け取らない相続人との間の不公平がとても見逃すことができないほどに大きいような特別の事情がある場合は、特別受益に準じた扱いになります。 |
| 債務の肩代わり | 被相続人が相続人の債務を肩代わりして支払った場合には、通常は、その相続人に対して求償することができるので、それだけでは、特別受益にはなりません。 ただし、被相続人が求償権を放棄したような場合で、肩代わりした債務の金額が遺産の前渡しといえる程高額な場合には、特別受益に当たります。 |
| 死亡退職金 | 死亡退職金については、労働協約や就業規則により、死亡退職金を受け取る遺族の生活保障という趣旨が明らかなときは、特別受益には当たりません。 他方、 個人企業の役員が死亡した場合のように、死亡した本人の長年の功績に報いるという色彩が強い場合には、特別受益に当たるとされることが多いです。 |
| 遺族給付 | 遺族の生活保障のために支払われるものは、特別受益に当たりません。 |
| 被相続人の建物の無償使用 | 被相続人と同居していた場合には、特別受益には当たりません。 同居していなかった場合にも、特別受益にあたらないとされることが一般的で、家賃相当額が特別受益にあたるようなことはありません。 |
| 相続人の配偶者や子が受けた贈与 | 相続人ではない者への贈与は、原則として特別受益にはなりません。 ただし、 名義上は、配偶者や子に対する贈与であっても、実質的には、相続人への贈与である場合には特別受益とされる可能性もあります。 |
特別受益の持ち戻し
遺留分の計算をする際は、生前贈与で先に渡した財産も合わせて計算する必要があります。
遺留分を考えるうえでは、この特別受益を亡くなった時の遺産に足し戻して考えなければいけません。これを「特別受益の持戻し」といいます。
特別受益の評価は、死亡時(相続発生時)とされています。
相続税の計算においては、持ち戻されるときは贈与時の価格なので、遺留分を計算する時の死亡時とは異なります。
また、持ち戻しする対象期間も、相続税の計算においては「生前贈与加算」で規定されている3年~7年ですが、遺留分を計算する時は10年分となります。相続人以外に対して行われたものは1年間が、遺留分の計算の対象となります。
なお、「生前贈与加算」の詳細については、以下の記事で詳しく説明していますのでご参照下さい。
「特別受益」の時効
特別受益に時効という概念が存在しません。
極端な話、20年前でも30年前でも、特別受益となる生前贈与を受けていた場合には、持戻しの対象になります。
ただし、調停や裁判となった場合には、遺留分を主張する人が「特別受益」が発生したことを立証しなければなりません。
「特別受益の持戻し免除」
通常であれば、親から子供に対して新居の購入費の援助をしたなら、それは「特別受益に該当」し、遺産分割の際は、持戻して分け方を決めるのが原則ですが、
贈与した人が、『生前贈与はするけど、死んだときに「特別受益」として持戻さなくていいよ』という意思表示をしていた場合には、持戻さなくてよいとされています。
これを『特別受益の持戻し免除の意思表示』といいます。
法律上、この制度は口頭だけでも成立するとされています。
- 遺産分割協議の「特別受益の持戻し免除の意思表示」は有効とされています。
- 遺留分の計算時に「特別受益の持戻し免除の意思表示」することは無効とされています。
- 婚姻20年以上の夫婦間で自宅の贈与(又は遺贈)があった場合には、特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

まとめ
ご説明した様に「生前贈与加算」と「特別受益」とは別物であり、「生前贈与加算」は相続税を軽鎖する時の持ち戻しの制度であり、遺留分の計算時の持ち戻しとは別のものです。
「特別受益」では、10年間の生前贈与分の持ち戻しをしなければいけないということです。
この話を勘違いしてしまうと、遺留分の額が誤ってしまい、「遺留分の侵害」が発生してしまうことになります。
遺留分の請求が発生した場合には、相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
以下の記事では、相続税に詳しい税理士を紹介しています。

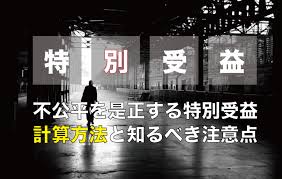

コメント