相続の話をする時、遺贈という言葉を良く耳にします。
- 遺贈って何なんだろう?
- 相続と遺贈は何が違うの?
- 遺贈は相続と贈与どっち?
- 相続時の税金の違いは何?
今回は、そんな疑問にお答えします。

遺贈とは
相続と遺贈の違い
「相続」とは、思想や教えを引き継いでいくという意味があり、亡くなられた方の財産を、法律で定められた相続人(法定相続人=配偶者・お子さん・ご両親・ご兄弟など)が引き継ぐことです。
一方、「遺贈」とは、遺言書により、無償で財産を譲ることです。法定相続人でも構いませんし、法定相続人以外の第三者の方、あるいは法人が受遺者になることも可能です。
つまり、遺言書による故人からの贈与となりますが、既に渡す人が亡くなっているため両者の合意が必要な贈与とは考えず、相続として扱うという違いがあります。

- 遺贈:財産を渡す人が遺贈者、受け取る人が受遺者
- 相続:財産を渡す人が被相続人、受け取る人が相続人
尚、遺贈をする人を「遺言者」と呼ぶと書きましたが、遺贈によって財産を受けとる人のことを「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。
「遺贈」と「相続」の違い
相続と遺贈では、「亡くなられた方の財産を特定の方が譲り受ける」という意味で同じではありますが、法律上は明確な違いがあり、相続する財産に掛かる税金や手続きも異なってきます。
更に、遺贈と似たようなものに、「死因贈与」があります。
こちらは、生前に自分の財産を誰にゆずるかを決めていることまでは同じですが、死亡を原因とした贈与契約という点が異なります。
契約なので、遺贈と違って受けとる相手とのあらかじめの合意が必要で、合意があれば法定相続人でもそれ以外の第三者でも、財産を受けとれます。
遺贈も死因贈与も死亡を起因として財産を受けとるという点では相続と同じですので、贈与税ではなく相続税がかかります。
第三者が遺贈を受けた場合には、法定相続人が納める相続税の2割増しの税金が課せられます。
また、遺贈や死因贈与で個人ではなく法人が財産を引き継ぐ場合には、相続税ではなく法人税がかかります。
第三者が遺贈によって受けとることになった財産が不動産の場合には、相続税のほかに不動産取得税が課されます。
一方、相続の場合には、不動産取得税は非課税です。
不動産を登記する場合には、登録免許税が必要になります。登録免許税は、法定相続人は0.4%ですが、受遺者が法定相続人以外の場合には2%と5倍かかります。
遺言書の書き方
「終活を始めるにあたり、遺言書を書こうと考えている。財産を渡すのは息子2人と、いつも世話をしてくれている長男のお嫁さん。遺言書の書き方について調べていたら、渡す相手によって、「相続させる」、もしくは「遺贈する」と書き方を変えるようだが、いったい何が違うのだろうか?」
「不動産を妻に相続させる」「預貯金を息子の嫁に遺贈する」などの文言は遺言の中でよく見かけます。
どちらも遺言者が死亡した場合に特定の者が財産を取得することになるという意味においては似ているのですが、実は大きな違いがあります。
遺言書を作成するとき、法定相続人に対しては「相続させる」「遺贈する」という言葉の両方が使えますが、法定相続人以外の方には必ず「遺贈する」という言葉を使います。従って、法定相続人以外に対して「相続させる」と書くことはできません。
また、「与える」「譲る」「あげる」という言葉を使われる場合、相続では「遺贈する」と同様の意味として扱われます。
法定相続人には、「相続させる」方が、手続きや税金面でメリットがあるといえますので、遺言書を作成する際には、必ず「相続させる」と記載することをお勧めいたします。

遺贈には2種類ある
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。その内容や遺贈の方法によって大きな違いがあり、受けとる側や相続人にも大きな影響を与えるので注意が必要です。
包括遺贈とは
「包括遺贈」とは、遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産全体の何割、何分の何というように割合によって与える遺贈を指します。
たとえば、「Aさんに自分の資産の2分の1をゆずる」というように遺言書には記載されます。
ただし、その遺産のなかには、借金などのマイナスの資産(負債)が入っている場合もあります。
受けとる側は、その負債も割合に応じて併せて引き継ぐことになるので、注意が必要です。
特定遺贈とは
「特定遺贈」とは、あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定して、与える遺贈のことです。
たとえば、「Aさんには不動産を、B法人には現金を、Cさんには株式を与える」というように遺言書には記載されます。

遺贈の放棄もできる
遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、契約である死因贈与とは異なり、あらかじめ受遺者の受けとりの意思を聞いておく必要はありません。
したがって、もしも「包括遺贈」でマイナスの遺産も併せて受けとることになる場合などには、受遺者は遺贈の放棄をすることができます。
包括遺贈の放棄方法
「包括遺贈」で誰かの遺産を受けとることになったけれども、遺贈を放棄したい場合、自分に対して包括遺贈があった事実を知った時点から3か月以内に手続きをしないとなりません。
もし、3か月が過ぎても遺贈の放棄の申述をしなかった場合には、受けることを承認したとみなされます。
包括遺贈の場合には、相続人と同じ権利や義務をもつことになるので、相続放棄と同じ手続きとなります。
手続きは、相続放棄と同様に裁判所に申述をします。遺贈があったことがわかる書類と申述書を、遺言者が亡くなった住所地の管轄の家庭裁判所に提出します。受理・不受理の結果は、書面で連絡が来ます。
特定遺贈の放棄方法
「特定遺贈」を放棄する場合は、遺贈義務者である相続人か遺言執行者に対する意思表示だけで行えます。
通常は、トラブルを避けるために内容証明で遺言執行者に送ります。
また、包括遺贈とは異なり、「〇月〇日までに放棄の手続きをしなければならない」といった期間は定められていません。
ただし、受遺者が承認も放棄も意思表示をずっとしないままでは、相続人や遺言執行者などの利害関係者は遺産の分割ができないことになり、非常に迷惑します。
そのため、遺贈義務者や利害関係者は、期間を定めてその期間内に遺贈を承認するか放棄するかを決めるように受遺者に催告することができるようになっています。
受遺者が決められた期間内に回答をしなかった場合には、承認したものとみなされます。

遺贈のメリットとデメリット
では、生前贈与や死因贈与などではなく、「遺贈」という形をとることにメリットはあるのでしょうか。
また、逆に遺贈することでのデメリットはあるのでしょうか。あるとしたら、どのようなことでしょうか。ここでは遺贈のメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。
遺贈するメリットとは?
相続では、原則、法定相続人にしか自分の財産を遺すことができません。しかし、遺贈であれば、たとえば孫や兄弟姉妹など、法定相続人ではない親族にも財産をゆずることができます。
遺言者が本当にゆずりたい相手を指定して財産を贈ることができるのです。
また、生前にお世話になった人などを受遺者にすることで、自分の感謝の気持ちを伝えることができます。
遺贈は個人だけでなく団体、法人も受遺者にできるので、支援しているNPO団体などに遺贈することで、自分だけでは成し遂げられなかった理想や思いを実現することもできるのです。
もし、受遺者が受けとりたくない場合には放棄することができるので、一方的な押し付けになることもありません。
また、法定相続人以外に財産をゆずりたい場合、財産分割のもめ事が起こることが多いものです。
このような場合、遺言の内容を非公開にしておくこともできます。
遺贈するデメリットとは?
遺贈にはメリットもたくさんありますが、デメリットもあります。
通常の遺贈では相続と同じく相続税がかかります。現金以外の遺贈の場合には、高額な相続税が負担となって受遺者がやむをえず遺贈を放棄することにもなりかねません。
せっかく生前にお世話になった人や団体に気持ちを表そうとしたのに税金がかせとなって放棄されるのは残念ですし、受遺者も故人の感謝の意を税金が理由で受けとれないとなると、申し訳ない気持ちになります。
さらに、「遺留分」によるトラブルの恐れもあります。法定相続人には、法律で最低限相続できる割合がそれぞれの立場ごとに決められています。それが「遺留分」です。
しかし包括遺贈によって全財産を特定の受遺者に贈るとされた場合、相続人は何も相続できなくなります。そのような場合には、遺留分を請求することができます。
この請求を「遺留分侵害請求」といいます。
また、遺言書の書き方には一定のルールがあります。その遺言書のルールが守られておらず無効になると遺贈ができなくなることもあります。

遺贈と相続で異なる点
相続と比較して遺贈は手続きや税金も異なってきます。
その違いについて以下に説明します。
不動産相続への影響
遺贈と相続では、不動産の承継に大きな違いがあります。
相続による承継は事務負担や税負担が軽くなりますが、遺贈の場合は逆となり、登記申請に必要な書類が増えて、各種税金も高くなります。
具体的には以下のような違いがあるので、受遺者のメリットやデメリットを把握しておきましょう。

不動産の登記
相続や遺贈で不動産を取得した場合、その不動産を引き継ぐ方に名義変更する登記(所有権移転)手続きをおこなう必要があります。
所有権の移転は法務局に申請しますが、相続した不動産は相続の場合には単独で手続きできます。しかしながら、第三者に遺贈した場合は、登記申請には法定相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などが必要になります。
更に、遺贈の場合、通常の相続における所有権移転登記とは、手続きの方法が異なります。遺贈で不動産を取得する場合、関係各所からの許可や、承諾を得る必要がありますので、手続きが煩雑になります。
受遺者と法定相続人の関係が良好であれば問題ありませんが、対立関係にあると、必要書類の取得に協力してもらえない可能性があるでしょう。
また、「遺贈する」遺言では登記をしなければ債権者に対して自分の権利を主張することができませんが、「相続する」遺言では登記がなくても債権者に自分の権利を主張することができます。
ただし、遺言執行者がいれば、受遺者と遺言執行者だけで登記申請できます。
このため、受遺者を遺言執行者に指定すれば、受遺者が遺言執行者として、ひとりで登記申請できることになります。
債権者への権利の主張
「相続させる」場合では、所有権移転登記がなされていなくても、債権者などに対して権利を主張することは可能です。(※法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことになっています。)
一方、「遺贈する」場合は、登記をしていなければ、債権者に対して権利を主張することはできません。
たとえば不動産の遺贈を受けた受遺者が登記をしない間に、相続人の債権者がその不動産を差し押さえた場合、受遺者は債権者に対抗できないということです。
不動産を遺贈された方は、すみやかに登記申請することをお勧めします。
農地の取得
農地には農地法が適用されており、取得するときは農業委員会、または都道府県知事の許可が必要となりますが、法定相続人の農地相続であれば許可は不要です。
一方、「遺贈」の場合は、包括遺贈(遺産の全部又はその分数的割合を指示するにとどまり目的物を特定しないでする遺贈)の場合以外は、農地法による農業委員会又は知事の許可が必要となります。
農地を取得する場合には、原則として農業従事者に限られるため、受遺者が農業従事者ではなかった場合は許可されない可能性が高いです。
農業委員会の許可がなければ所有権の移転登記もできないため、結果的に受遺者が遺贈を辞退(遺贈の放棄)するケースも考えられます。
「遺贈」の場合は、包括遺贈(遺産の全部又はその分数的割合を指示するにとどまり目的物を特定しないでする遺贈)の場合以外は、農地法による農業委員会又は知事の許可が必要となります。
従って、受遺者が農業に従事していない場合は、許可が下りずに登記ができない可能性があります。
また、特定遺贈であれば登録免許税の一般税率が適用され、不動産取得税も発生します。農地は特殊な相続財産になるため、農業従事者以外への遺贈はデメリットが大きいです。
一方、「相続」の場合は、農地法による許可は不要ですから、登記はスムーズにできます。
借地権の引き継ぎ
遺産が借地権や借家権の場合、「遺贈」では賃貸人(地主など)の承諾が必要となりますが、「相続」の場合は賃貸人の承諾は不要です。
賃借人(借主)が死亡した場合、賃貸借契約は相続人に承継されるため、継続して借りる場合には賃貸人の承諾を必要としません。
なお、遺贈によって不動産を取得すると、賃貸人へ譲渡承諾料を支払うケースもありますが、相場は借地権価格の10%程度になっています。

税金への影響
遺贈の場合は登録免許税が高くなる
不動産の所有者が変わった場合、新たな所有者には登録免許税が課税されます。
税額は「固定資産税評価額×税率」で計算しますが、遺贈と相続では以下のように税率が異なります。
- 計算式
- 遺贈の場合:固定資産税評価額×税率2%
- 計算式
- 相続の場合:固定資産税評価額×税率0.4%
相続では、土地や建物の評価額(固定資産税評価額)の0.4%であるのに対して、法定相続人以外に遺贈した場合は2%(法定相続人が遺贈された場合は0.4%のまま)と高くなります。
では、固定資産税評価額3,000万円の不動産について、遺贈と相続の税額を比較してみましょう。
- 計算式
- 遺贈の場合:3,000万円×2%=60万円
- 計算式
- 相続の場合:3,000万円×0.4%=12万円
登録免許税は現金一括納付が原則なので、高額な不動産を遺贈すると、受遺者が納税資金を準備できない可能性もあります。
不動産を遺贈するときは、受遺者にメリットがあるかどうかを十分に検討しましょう。
不動産を遺贈すると不動産取得税が発生
相続以外で不動産を取得したときは不動産取得税がかかりますが、相続で取得した場合は同税は課税されません。ただし、不動産を特定遺贈した場合には不動産取得税が発生します。
- 計算式
- 不動産取得税:固定資産税評価額×税率3%(2024年3月31日までの軽減税率)
- 計算式
- 税額の計算例:固定資産税評価額3,000万円×3%=90万円
特定財産の遺贈を特定遺贈といい、不動産を遺贈すると不動産取得税が課税されますが、財産の取得割合を指定する包括遺贈であれば課税されません。
包括遺贈の場合、受遺者と相続人は同等の地位といえるため、不動産取得税の課税についても相続人と同じ扱いになっています。
受遺者は相続税の基礎控除に影響しない
相続税には基礎控除があり、以下のように計算するため、法定相続人の数が多いほど控除額も高くなります。
- 計算式
- 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人が1人であれば3,600万円、2人の場合は4,200万円となり、基礎控除額が高くなると相続税の課税対象額は減少します。
遺産総額が基礎控除以下であれば相続税は非課税となり、税務署に申告する必要もありません。
ただし、計算式には法定相続人しか反映できないため、受遺者が何人いても基礎控除には影響しません。
遺贈には相続税の2割加算が適用される
相続税が発生する遺贈の場合、受遺者には相続税の2割加算が適用されます。
法定相続人以外への遺贈が2割加算の対象となるため、第三者だけではなく、孫や子供の配偶者に遺贈しても2割加算が適用されます。
また、亡くなった方の兄弟姉妹や祖父母については、法定相続人になるケースでも2割加算の対象となります。
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2

遺贈における注意点
包括遺贈する場合、納得できない相続人から遺留分を請求されると、遺言者が考えていた割合で受遺者に財産をゆずることができないこともあります。
そして、せっかく感謝の気持ちを示そうと思っていた受遺者を、相続トラブルに巻き込むことになりかねません。こうした争いは長びくことも多いので、なるべく避けたいものです。
そうしたトラブルが起きるリスクを減らすためにも、基本的には包括遺贈ではなく特定遺贈のほうが望ましいといえます。
特定遺贈の場合にも、相続税などの税金が受遺者の負担にならないように配慮することが大事です。
遺言者として遺贈を行う場合には、遺言書を作成する前に遺留分が請求される可能性をあらかじめ考慮しておくとよいでしょう。
遺留分を踏まえたうえで、誰に何をゆずるかを決めます。また、同時に受遺者に課せられる税金のことも配慮する必要があります。
また、遺贈には条件を付けることができます。たとえば、事業を継続することを条件に個人または法人に株式をゆずったり、家屋を維持することを条件に個人または団体に遺贈する場合などがあります。
ただし、注意したいのは、遺贈する相手に税金がかかる場合です。税金が負担にならないように配慮することが重要になります。
まとめ
民法や税法には様々な優遇措置があり、相続人の地位が脅かされる、あるいは相続税のために自宅を売ることがないよう配慮されています。
ただし、適用できるケースは相続に限られており、対象者も特定の相続人となるため、財産の取得だけが遺贈のメリットといえるかもしれません。
受遺者の事務負担や税負担は相続よりも重くなっていますが、受遺者となる場合には想定外の財産を取得することでデメリットも被ることを認識しておいた方がよいでしょう。
遺言者としてお世話になった方や団体に遺贈したいなら、トラブルに巻き込むリスクをできるだけ減らすように遺言書を遺す必要があります。
また、あなたやあなたの近しい人が受遺者になった場合に備え、まずは遺贈の流れを把握しておくことが大切です。
そして、もしも受遺者になった時には、どういう種類の遺贈なのか、その内容を精査して、相続するかどうかをしっかり検討しましょう。
相続や遺贈についての専門的なアドバイスが欲しい方は、専門知識が豊富な税理士への相談も検討してみてください。
以下の記事では、相談可能な、相続の専門家を紹介しています。

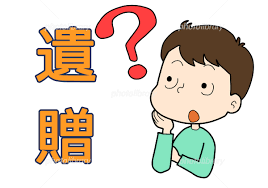
コメント