相続が発生した時に、先祖代々受け継がれてきた土地が「農地」の場合は、一定の要件を満たせば「農地の納税猶予」の特例が受けられます。
この「農地の納税猶予」の特例は、農地を受け継いだ後にずっと農業を続けていく考えの人にとっては大変お得な特例です。
適用するには、いくつかの要件があるので、しっかりと理解したうえで活用することにより、納税自体が免除」されますので、農業をされている方はキチンと理解しましょう。
今回は、「農地の納税猶予」の特例についてご説明します。

「農地の納税猶予」の特例とは
「農地の納税猶予」の特例は、相続が発生することにより農地が細分化されることを防止し、農業後継者が農業を継続して実施して貰える様にすることを目的として設けられた特例です。
一般的に、相続は3代発生すると、財産が無くなってしまうとよく言われる程、納税額が高いです。
しかしながら、農業を営んでいる方の農地が3代で無くなってしまうと、誰もお米や野菜を作れなくなっていまい、日本国内で食料の自給ができなくなってしまいます。
このため、農業を保護する観点からこの制度が制定されました。
「農地の納税猶予」の特例は、農業を営んでいる方が死亡した時、後継者が農地を遺贈されたり、相続したりする場合でその後も引き続き農業を営む場合に限り、一定額までの相続税の納税を猶予し、条件が整えば最終的に納税が免除されるという制度です。
「農地の納税猶予」が適用される農地の要件
農地とは「農地・採草放牧地・準農地」のことを指しますが、「市街化区域(生産緑地地区・田園住居地域・それ以外)」と「市街化区域外(市街化調整区域・非線引き区域)」にある農地等が、納税猶予の特例の対象となります。
適用される農地の例としては次のものも含まれます。
- 災害や病気など一時的な理由で現在は耕作されていないものの、いつでも耕作ができる休耕地
- 植木が植栽されている土地
- 販売を目的に盆栽を育成管理している土地
なお、家庭菜園や工場の敷地で一時的に耕作している土地、観賞用の盆栽を育てている土地は農地には該当しません。
被相続人の要件
被相続人が以下のいずれかに該当する人である必要があります。
- 死亡の日まで農業を営んでいた人
- 生前一括贈与(贈与税の納税猶予)をした人
- 死亡の日まで特定貸付け、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた人
相続人の要件
相続人は、以下のいずれかに該当する該当する人である必要があります。
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後、引き続き農業経営を行う人
- 生前一括贈与を受けた受贈者
- 相続税の申告期限までに特定貸付け又は認定都市農地貸付け等を行った人

納税猶予税額の免除要件
相続税の納税猶予税額が免除となる要件については、農地等の都市計画区分及び地理的区分によって異なります。
基本的には、農業経営する相続人の死亡をもって免除となるので、終身営農が要件ですが、一部の条件下では、期間20年で免除となる農地等もあります。

なお、農業経営を行う相続人が後継者に生前一括贈与した場合も相続税の納税猶予税額が免除となります。

「農地の納税猶予」の計算方法
本「農地の納税猶予」の特例を適用することにより、農地の評価額が、「農業投資価格」に置き換えることが可能となるため、大幅に、相続税の節税を行うことが可能となります。
なお、農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として国税局長等が決定した価格をいいます。
※農業投資価格は、国税庁ホームページの「路線価図・評価倍率表」で、取得した農地等の所在する都道府県ごとに確認することができます。
納税猶予税額 = 通常の評価方法による相続税の総額 ー 農業投資価格による相続税の総額
なお、農業相続人が複数いる場合人の納税猶予税額は、次の計算式により按分します。
各農業相続人の納税猶予税額=納税猶予税額の総額x各相続人にかかる金額
÷(通常の評価額 ー 農業投資価格による評価額)
農地の納税猶予を使用した相続税の計算例
特例を適用して相続税を計算した具体的な例を以下に示します。
【具体例】
法定相続人の数:1人
自宅:1億円
農地:[評価額]5億円 [農業投資価格]1,000万円
現金:1,000万円
「農地の納税猶予」を使用しない場合
相続税額 = 遺産総額(1億円+5億円+1,000万円) − 基礎控除額(3,000万円+600万円×1人)
=基礎控除後の遺産額(5億7,400万円) × 相続税率(50%) − 控除額(4,200万円)
= 2億4,500万円
「農地の納税猶予」を使用した場合
相続税額 = 遺産総額(1億円+1,000万円+1,000万円) −基礎控除額(3,000万円+600万円×1人)
=基礎控除後の遺産額(8,400万円) × 相続税率(30%) − 控除額(700万円)
= 1,820万円
「農地の納税猶予」を使用すると大変お得
納税が猶予される金額は通常の計算で算出した相続税額から、特例を使って算出した相続税額を差し引いた額です。
上記の例では、【2億4,500万円−1,820万円】= 2億2,680万円が納税猶予される金額となります。(納税猶予は、納税を待ってくれるだけなので、将来的には支払わないといけません。)
更に、生涯農家を続ければ、この2億2,680万円は納税が免除されます。
非常にお得ですよね。

相続税の納税猶予の手続き要件
相続税の納税猶予の適用を受けるためには、適用要件を満たすだけでなく、以下のような手続き要件も満たす必要があります。
納税猶予の利用に必要な書類
農地の納税猶予の特例を適用されるには、以下の書類をそろえて税務署に提出する必要があります。
入手先もそれぞれ異なるので注意してください。
なお、納税猶予を受け続けるには、農業を継続していることの届け出を3年ごとに行う必要があります。
| 必要書類 | 入手先 |
| 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 | 農業委員会 |
| 特例適用農地の明細書 | 農業委員会 |
| 納税猶予の特例適用の農地の該当証明書 | 市役所 |
| 担保提供書 | 税務署 |
| 抵当権設定登記申請書 | 法務局 |
相続税の申告手続
- 相続税の申告書に所定の事項を記載し期限内に提出すること
- 農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供すること
- 相続税の申告書には相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類など一定の書類を添付すること。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書は、農業委員会に申請して発行してもらう必要があります。
しかしながら、適格者証明書は発効までに日数がかかる場合があるので、相続税の申告期限に間に合わせる為には、早めに申請しておく必要があります。
納税猶予期間中の継続届出
「農地の納税猶予」の特例は、1回申告して終わりという訳ではなく、納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続きこの特例の適用を受ける旨と特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書(継続届出書)を提出する必要があります。

「農地の納税猶予」の打ち切り
「農地の納税猶予」の特例は以下の事由が発生した場合には打ち切りとなります。
打ち切りとなった場合には、猶予されていた相続税の全部又は一部とその税に対する利子も納税しなければなりません。
全額打ち切りの事由
- 特例の適用を受けた農地等の面積の20%超を譲渡、贈与、転用、耕作放棄等した場合
- 相続人が農業経営をやめた場合
- 担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかったとき
- 継続届出書を提出しなかった場合 等
一部打ち切りの事由
- 特例の適用を受けた農地等の面積の20%以下を譲渡、贈与、転用、耕作放棄等した場合
- 特例の適用を受けた準農地について、相続税の申告期限後10年以内に農業の用に供していない場合 等
つまり、土地を手放さず農業経営を継続して行い、決められた諸手続きをおこなっていれば大丈夫ということです。

農地相続のルール
農地は、「農地法」という法律によって規制されており、土地のなかでも特殊な扱いをされていて、一般の土地のように自由に売買をしたり贈与をすることができません。
農地相続に許可は不要だが届出は必要
農地を売買したり、贈与をする場合には農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。
一般の土地とは違って、自由に名義を変更することはできないのです。
これは食糧自給の観点から優良な農地を確保しておきたいことと、農業離れを防止するためのものです。ただし、相続に限っては許可は必要ないことになっています。
許可は必要ありませんが、届け出は行わなければならないという決まりがあります。
農地を相続した場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に地域の農業委員会に届け出なければなりません。
もしこれを怠った場合は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
なお、専用の届出書は農業委員会に用意されています。
農地の売買や贈与には許可が必要
くり返しになりますが、農地は自由に売ったり買ったり、あるいは贈与したりすることはできません。それが許されると国土から農地がどんどん減っていくことになりかねないためです。
国土の狭い日本においては食糧を生産する農地は貴重な存在なのです。
しかし、農業を継ぐ気持ちのない相続人にとっては逆に足かせになってしまうことも否めません。
農地を農地のまま売却するには農業委員会の許可が必要で、その売却先も農業を営んでいることが最低限の条件となるからです。
そのため、売却には時間がかかってしまいます。
なお、農地を農地のまま売却する場合に必要な許可は農地法で「第3条許可」と呼ばれています。
農地を勝手に宅地にできない
「農地転用」にて、農地を農地以外の目的に利用するということも考えられますが、農地転用する場合は、農地法でいう「第5条許可」が必要で、都道府県知事の許可が必要となります。(指定市町村の場合は市町村長。例外的に農業委員会の場合も)。
また、農地を売却しないで自分用の宅地にする場合にも、農地法でいう「第4条許可」が必要で、都道府県知事の許可が必要になります。
更に、「農地転用」した場合には、「農地の納税猶予」の特例は、打ち切りとなってしまい、猶予金額を返済しなければならなくなります。

まとめ
この特例は大変お得ですが、「農地の納税猶予」の特例はあくまでも納税の猶予です。
農地は、農地法により縛られており、簡単に土地を自由に売買したり、転用することはできません。
このため、この特例を使用する場合には、一生農業を実施していくという強い意思が必要となります。軽はずみに相続してこの特例を使用してしまうと、打ち切りに合い、後から莫大な税金を支払わなければならなくなります。
良く考えてから、この特例を使用するかしないかを決断して下さい。
なお、決断に困った場合には、相続に詳しい税理士にご相談下さい。
以下の記事では、相続に詳しい税理士をご紹介していますので、是非とも参考にして下さい。

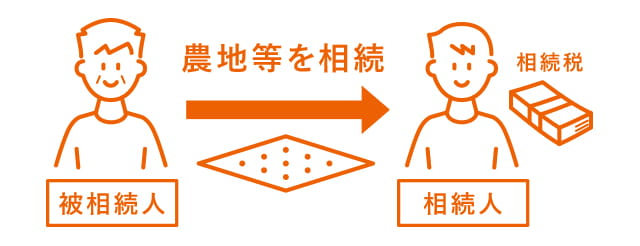
コメント